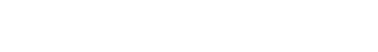APDA 生命の安全教育:尊厳を守る教育に関するアジア議員会議
2025.10.7 日本・東京
アジア人口・開発協会(APDA)は、10月7日、「生命の安全教育:尊厳を守る教育に関するアジア議員会議」を、プラン・インターナショナル・ジャパン(PIJ)との共催、国際人口問題懇談会(JPFP)生命の安全教育プロジェクトチーム(PT)及び国際家族計画連盟(IPPF)の協力のもと、都内で開催しました。開会式では、堀内詔子JPFP PT座長代行の進行の下、武見敬三APDA理事長が主催者挨拶を行い、国会議員のネットワークを活用して人権やジェンダーなど共通の課題に取り組む重要性や、若者の幸福と人材育成への貢献を強調しました。続いて上川陽子JPFP会長・AFPPD議長が基調講演を行い、これまで取り組んできた刑法改正や保護体制の充実強化を紹介し、子どもたち自らが心と身体を守る力を育む「生命の安全教育」について、その経緯と意義を説明しました。
セッション1「特別講演:日本の現状と課題」では、丸の内の森レディースクリニック理事長・宋美玄氏が医療現場の視点から日本の現状と課題を紹介し、宮路拓馬議員(外務副大臣)とセッション議長を務めた寺田静JPFP幹事がそれぞれコメントを述べました。セッション2「事例報告①:東・東南アジアにおける教育アプローチ」では、日本、韓国、台湾、その他アジア諸国の教育事例が紹介されました。日本では文部科学省(MEXT)が、性犯罪・性暴力の根絶を目指し、自己尊重と他者尊重を発達段階に応じて育む「生命の安全教育」を推進しています。韓国のLALA性文化研究所はデジタル性暴力予防の教材等を紹介し、台湾ジェンダー平等教育協会(TGEEA)は、包括的性教育(CSE)が全教科に組み込まれていることを紹介しました。IPPF東・東南アジア・大洋州地域事務局のMagdalena Nadya氏は、地域の現状と、CSE実施のための国家基準整備、教員研修、デジタル教材活用など5つの提言を示しました。
セッション3「事例報告②:立法・政策事例」では、フィリピン、日本、タイ、インドネシアの事例が報告されました。フィリピンでは、年齢や発達段階に応じたリプロダクティブ・ヘルス(RH)及び性教育を義務付ける「責任ある親であることとRHに関する法律(Responsible Parenthood and Reproductive Health Law)」を導入している一方、地域格差や誤情報の課題が指摘されました。日本の事例では、牧島かれんJPFP副会長が、若者のデジタルリスクと、その対応について説明しました。タイは若年妊娠防止、中絶、CSE教育、LGBTQ権利などの政策を統合的に実施しており、インドネシアではARH(思春期RH教育)として全国規模での教育を推進しています。セッション4「次なるステップ:制度設計と社会理解の促進戦略と国際的連携」では、牧原秀樹 前法務大臣の進行の下、ニュージーランド、カンボジア、オーストラリア、日本の事例が議論されました。Catherine Wedd議員(ニュージーランド)は、子どもをSNSやサイバー暴力から守る法の重要性を強調しました。在日オーストラリア大使館のStuart Watts公使(政務)は、同国で導入されたソーシャルメディア年齢制限法(SMMA)について説明しました。カンボジアは、内戦後のCSEのカリキュラム導入、デジタル教材やユースアプリの活用、NGOとの連携による全国展開について説明しました。最後に、PIJは日本での若者への情報提供の不足を指摘し、展開中の「SRHR for JAPAN」キャンペーンについて紹介しました。閉会式では、カンボジアのYos Phanita上院議員及び阿部俊子議員・JPFP生命の安全教育PT座長(文部科学大臣)が挨拶を行い、会議を締めくくりました。会議には、オンライン参加も含め10を超える国と地域、約60名が参集し、生命の安全教育や同様の取り組みに関する法的枠組みや学校教育の現状と課題について共有し、優良事例や教訓を学ぶ貴重な機会となりました。